地獄湯ノ沢でも表層雪崩が発生しています。
発生事例2 2007/1/7
地獄湯ノ沢の標高1150m付近で表層雪崩。1名が完全埋没したが、ビーコン・ゾンデで場所を特定、
スコップで掘り救出。(雪崩発生から救出まで、所要15分程度)
熊谷トレッキング同人 2007.1.7 八甲田山雪崩埋没事故報告
(発生経緯、装備、救助に関し、とても参考になる報告です。)
発生事例1 2006/2/初旬
地獄湯ノ沢夏道交差部付近で表層雪崩に遭い首まで埋没したが自力脱出
(某掲示板書き込み記事、その後本文削除され、人づてにメール照会したが返答無しのため、
未確認情報です。)
検証 地獄湯ノ沢の表層雪崩
1.発生位置
地獄湯ノ沢左岸 1150m付近(発生事例2資料より推定、写真のA点付近〜B点付近)
地獄湯ノ沢左岸 1170m付近(発生事例1より推定)
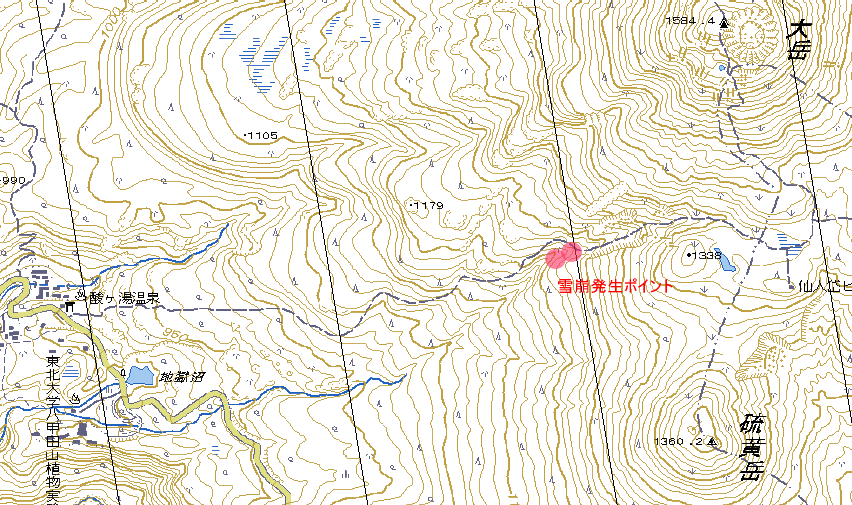
2.地獄湯ノ沢の写真
2007/9 撮影
・高度計で確認していないため、標高は概算。
・雪崩発生ポイントは、写真のA点付近〜B点付近および夏道合流点付近と推定されます。
・A点〜(B点)〜夏道合流点間は概ね距離150〜200m程度(記憶があいまい)。
 A点・B点
A点・B点B点は上流の岩場、A点は下流の土壁部。沢はA点・B点で方向を変えている。
B点には、右岸から小さい沢状
A点上部?の斜面
夏道から見た、地獄湯ノ沢左岸上部
・以下写真は、下流から上流に登りながら撮影
沢から南八甲田(下流方向)を振り返る
この先の土壁(A点)で、沢が方向を変え始める
沢の方向が変わり始める(B点を過ぎると完全に方向が変わる。)
B点が見える
B点で完全に沢の方向が変化する。
標高1170〜1180m付近
以下、夏道合流点から上流部
硫黄臭のある付近
コメント
・表層雪崩回避のためには、硫黄岳ルート(硫黄岳鞍部経由仙人岱小屋)が考えられます。
・基本的にある程度傾斜のある沢筋ですので、雪崩の危険性はあり。
・春山の締まった雪の状態と、厳冬期の表層雪崩の起こり得る雪の状態は全く別ものなので注意したい。
・雪崩事例は左岸だけであるが、右岸にも傾斜大の斜面があるので、右岸の雪崩にも注意を払いたい。
参考
雪崩・亀裂事例マップ